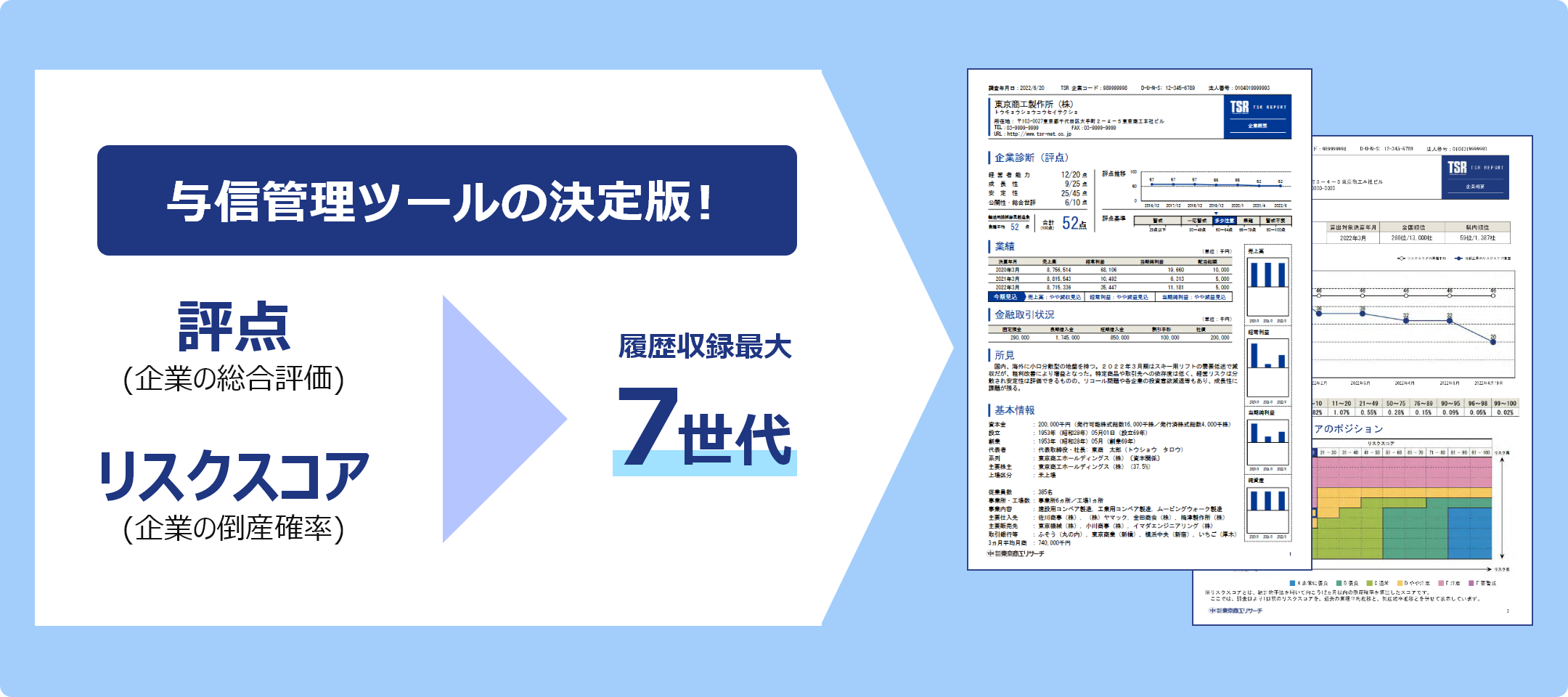民事再生法
企業が事業を継続して再建を図る「再建型」の倒産手続きのことです。平成12年4月「和議法」に代わり施行され、主に中小企業が適用していますが、個人も対象にしています。会社更生法に比べ手続きが簡易かつ迅速で、再生計画の認可要件が出席した再生債権者等の過半数、債権総額の2分の1以上の同意などに緩和され、再生計画成立が比較的容易なことが特徴です。
(1)民事再生法成立の背景
アメリカの倒産法チャプターセブン及びイレブンを利用して「倒産」扱いされる企業数は日本よりはるかに多い。しかし、アメリカは消滅して行く企業より、新しく創業される企業のほうが更に多いと言われている。
1999年(平成12年)に倒産した15,352件のうち「倒産五法」によるものは2,651件、全体の17.2%であるがそのうち再建型の会社更生法、和議法、商法整理は209件、7.8%にすぎず、法的手続きのうち、92.2%は破産や特別清算という消滅型なのである。91年には再建型の比率は17.4%であった。これは単に景気の良し悪しによるとは言えない。日本の企業の再建率の低さ、これは失敗を許さない国民性にもよろうが、一度事業に失敗したら、まず再起出来ないという現実がある。それどころか倒産事業者を待っているのは殆どの場合、夜逃げ、一家離散、自殺といった悲惨な運命である。これでは若者がリスクを背負うより、公務員か大企業に勤めようとするに決まっている。社会全体に独立心、創業心が失われて行くことになる。チャレンジ精神を失わせる原因の一つが日本の倒産法にあるという認識が、新倒産法制定の大きなモーメントとなっている。
1998年3月発表された中小企業庁の「平成9年度倒産法制に関する調査研究報告書」に10年前に法的形態で再建を目指した180社の企業の追跡調査結果が記載されている。内訳は会社更生法50社、和議法100社、商法整理30社。10年後に債務完済が出来た企業は更生法10社、和議法17社、商法整理5社、消滅したのが会社更生法24社、和議法72社、商法整理17社という結果である。10年以内に89社、63%が消滅しているが、なかでも和議法申請企業の消滅は72%に及んでおり、その実効性は殆ど失われているというのが現実と言える。
この理由は和議法が大正11年、商法整理にいたっては明治32年に施行された法律でその後何度かマイナーチェンジはあったものの、基本的な骨格が既に時代にそぐわなくなっていることによる。再建型と言われるにもかかわらず、この三法が適用される条件が殆どの場合「債務超過」つまり、もはや会社の資金繰りが立ちゆかなくなった状態でなければいけないということが、再建を困難なものにしている最大の理由である。
欧米と日本の会社の大きな違いは、日本の場合90%以上が大株主イコール社長という、実質的な個人企業であること、つまり、会社と個人が一体であることが、トコトンまで頑張ってしまわざるを得ない原因になっている。自分の資産をすべて注ぎ込んでの経営であるため、会社の破綻イコール個人生活の破綻となってしまう。大企業が潰れてもサラリーマン社長が夜逃げをしたり、首吊りをすることはまず、あり得ない。こういう日本の中小企業の特質は一朝一夕にして変えることは出来ないが、倒産法の改正によっては再建の可能性をかなり増やすことは出来るであろう。企業は平均2月商分の債務超過で経営に支障を来し、 4月商分の債務超過で完全に行き詰まる。債務超過前に倒産法が適用可能となれば再建率は50%を超すであろう。そのことによって、債権者の債権回収率は高まり、債務者の個人生活の破綻や、会社の経営資源の散逸が防げるならば、国民経済的見地からも大きなプラスとなる。また、一度失敗しても再起のチャンスが生まれるならば、今よりもっと多くのチャレンジャーが経営に参入し、新規創業が増えていくことになる。政府が景気対策、雇用対策として起業を促進すべく資金的なバックアップに力を入れているが、倒産法の改正は別の方向から起業促進の効果をもたらすことになる。
平成12年4月1日の当法施行と同時に「和議法」は廃止、「商法に基づく会社整理」は空文化している。
(2)民事再生法の要点(和議法と異なる主要な項目)
- 手続開始時期の早期化
和議の場合は破産と同様、債務超過が条件となるが、民事再生法では「破産原因の生ずるおそれ」または「事業の継続に著しい支障を来すことなく債務を弁済できないこと」が条件、つまり債務超過でなくても申立てが出来る。 - 再建計画可決の条件緩和
和議の場合は出席債権者の過半数で且つ、届け出総債権額の4分の3以上の者の同意が必要だったが、民事再生法では書面での決議も含め出席債権者の過半数で且つ、議決権総額の2分の1以上の者の同意と、条件が緩和されている。 - 不動産担保の解除
再建のために維持活用が必要な不動産に担保設定がなされている場合、これを時価で評価し、その金額を弁済することで担保権を解除させることができる。つまり担保設定額と関係なくその物件だけの時価分を支払うだけで営業上必要な不動産の利用が出来る。 - 保全措置の充実(包括的禁止命令)
債務者(当法では再生債務者と称する)が多数の資産を有する場合、個別のケースごとに債権者(当法では再生債権者と称する)の法的権利行使(競売など)を中止させる手続をとっていたのでは手におえなくなる恐れがあるため、再生債務者の全ての資産について、すべての再生債権者を対象に法的権利の行使を中止させる保全処分である。 - 再建計画履行確保措置の充実(監督委員、調査委員、管財人、保全管理人の設置)
計画認可後、再建計画を履行して行くケースは以下の3つのパターンがある。- (1)再生債務者本人が再建計画を履行する場合(DIP型)(これは従来の和議法のパターンであり、直ちに手続終了となるが、以後の履行確保措置が弱く、ウヤムヤのままになってしまうことが多かった)
- (2)このため、利害関係者の申立て、あるいは裁判所の職権で監督委員を選任し、3年間は再建計画の履行を監督する。監督委員の同意を得ない行為は無効となる。監督委員が注意を怠った場合は利害関係人に対し、再生債務者と連帯して損害賠償の責を負う。
- (3)再生債務者がその責に不適と判断された場合は管財人を選任し、再建履行まで管財人が管理する。
- ※民事再生法成立の事情から見ても、再建の実績を上げるべく、裁判所は当面のパターンを推し進めるものと予想される。
- 債権者委員会の設置により債権者の権利擁護を強める。
3名以上の再生債権者が債権者委員会を構成した場合、利害関係人の申立てにより裁判所はこの委員会が再生手続に関与(裁判所、監督委員、再生債務者への意見提出)することを認める。(ただし再生債権者の過半数がこの委員会を認めることが条件) - 管轄裁判所の特例
再生債務者が法人の場合、過半数を出資している子会社も再生申立てをする時は親会社と同一裁判所(再生裁判所と称する)へ行うことが出来る。会社と代表者の場合も同じ。 - 弁済分割期間の短縮化
弁済期間は会社更生法の20年に比べ10年と半減しており、それを超えると破産に移行する。 - 再生法利用対象者の拡充
商法法人はもとより、医療法人、学校法人、宗教法人、公益法人(社団、財団)そして個人でも可能である。
用語一覧へ